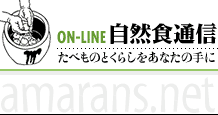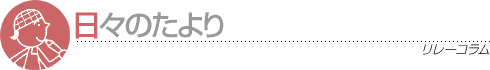6月29日
9時に原町産婦人科中央医院へ。
病院の待合室には毎日の放射線量が掲示されている。本日は病院内が毎時0.11MS(マイクロシーベルト)。屋外で0.86MS/h.
昨日到着したときから、NHKの撮影隊がJCFの行く先々に同行。1991ねんから、世界最悪の事故を起こしたチェルノブイリ原発の風下に位置し、事故直後偏西風にのって大量の放射能が森や大地に降り注いだ隣国ベラルーシに医療支援を続けてきたJCFだが、はからずも自分たちが暮らす足元を突然襲った原発事故と、まき散らされた大量の放射能の脅威に立ち向かわなくてなならなくなった。JCFの本部は長野県松本市。福島県との間に400キロほどの距離があるが、チェルノブイリよりは遙かに近い。スタッフも理事もそれぞれにたくさんの知り合いや身内もいる。が、そうしたことよりも、物言わぬ生き物たちも含め数百年にわたる子々孫々のいのちの連鎖に深刻な影響を及ぼす放射能の制御もかなわぬ原発に頼らない産業と暮らしをと声をあげてきたJCFだからこそ、これまでの支援活動のなかから学び取ったことを、チェルノブイリと福島を濃密に結んで、53基も原発をかかえる不安に押しつぶされそうになりながらもこの小さな列島でともに生きる道を開くために差しだしたいと動き出した。そうした行動の一端をカメラは追いかける。
今日の行動予定を打ち合わせた後、ホットスポットから逃れて、低線量地区の公民館に避難した保育園を訪ねて移動。南側よりいくらか汚染度は低いとはいえ、園児たちの朝の散歩はマスクをし、わずか30分ほど、公民館の周囲を歩くだけ。建物に入るときにはひとりひとりブラシではらってもらっていた。
公民館と道を隔てた林脇の側溝を線量計で測ると落ち葉がつもった場所と、なにもないところでは数値が倍くらい違っているのに驚く。保育園でも園児たちを雑木林には入らせないようにしているという。
保母さんたちにも線量積算バッチを交換してもらう。
午後は、地元で出産し、生後1ヶ月の赤ちゃんをかかえるお母さんの協力で、ご自宅を訪ねる。線量計測ガラスバッチを50人の妊婦、赤ちゃん、子どもたちにつけてもらっているが、そのお一人だ。ちょうど洗濯をしているところで、洗濯物はぜんぶ家の中でほしているとのこと。家の中の数値自体は屋外より屋内は当然低いが、赤ちゃんといっしょに寝ている採光のいい窓際に据え付けたベッドやその周りと部屋の入り口では倍近く違っていることがわかり、ベッドの位置をずらすだけでもいいのではとアドバイス。
屋外は前庭が地面から1mの位置で1.2マイクロsv(シーベルト)/時。家の敷地に入る道路際で1.15。雨樋の水の出口、車庫の波板トタン真下といった雨水の落ちるところではさらに高い数値に。これは原発からの放射能が流れつづけていることを意味するのだろうか? 爆発後空中に拡散し、格納容器を突き抜け下へ流れ出た放射能は今も出続けているのではないか、という不安が拭えない。
そこからさらに2カ所、高濃度汚染地区になっていて無人に近い場所で測定。いずれも高い数値。閉鎖された公民館の前の下水の入り口では4.5~6.5マイクロsv/hともっとも高い数値。水道も蛇口ちかくも2.4。松の木の下で2.3。道路際2.8。
明朝、私は帰京の途につくが、JCFは飯舘村へ入る予定。