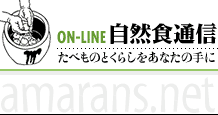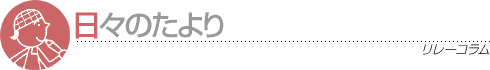7/30(土)~31(日)に東京・神楽坂の日本出版クラブを会場に、BOOK MARKET2016が開かれました。アノニマ・スタジオ主催のこの合同ブックフェアは今年で8回目。読者や書店員、出版社が直接交流できるイベントとして人気を集め、今年は32社の出版社が出展。2日間に訪れた人の数5000人(推定)と、これまでで最高のにぎわいに。7/30(土)には自然食通信社の著者お二人による対談が実現しました。
7/30(土)~31(日)に東京・神楽坂の日本出版クラブを会場に、BOOK MARKET2016が開かれました。アノニマ・スタジオ主催のこの合同ブックフェアは今年で8回目。読者や書店員、出版社が直接交流できるイベントとして人気を集め、今年は32社の出版社が出展。2日間に訪れた人の数5000人(推定)と、これまでで最高のにぎわいに。7/30(土)には自然食通信社の著者お二人による対談が実現しました。
東京・国分寺市で助産院を開業し30年。女性たちのこころとからだを丸ごと抱きとめ、開放感あふれるお産体験へといざなってきた矢島床子さん。布作家・早川ユミさんは高知県の山あいで、土を耕し自然とともに生きる知恵を土地のお年寄りたちに教わりながら、からだに寄りそう衣服をつくり続けて20年に。それぞれの分野で活躍するお二人に、〝いのち〟を〝つなぐ〟からだについて語り合っていただいた。
会場内には矢島助産院でのお産の様子を写した大きなパネル写真が飾られ、ダイナミックなお産の世界観に包まれながらスタート。
「70歳を超えたが、幸せな助産師をやってきた」そう話し始めた矢島さんはすでに5000人の赤ちゃんを取り上げてきたベテラン助産師さん。「赤ちゃんは、本来お母さんの小さな膣が大きく伸びきって生まれてくる。痛くてしょうがない。でもそれは自分で産んだ喜びに変わるための痛み」と、矢島さんは《自分で産む》ということにずっとこだわり続けてきた。
岐阜の山奥の農家で生まれ、子どもの頃は畑に出土する縄文時代の矢じり拾いに夢中。看護師を目指していた20歳の頃、自動車事故で峠から車ごと転落、意識不明の重体で今も目に麻痺が残る。事故後、助産師への道を勧められ、それが人生の転機になった。当時日本に入ってきたばかりのラ・マーズ法を広めた故・三森孔子助産師に師事し、病院では体験できない地域の開業助産師に出会う。自身も第3子の出産で初めて自宅分娩を体験。それまで子育てに無関心だった夫もお産に立ち合ったことで、子育てに対する意識が変わった。日常生活のなかで、布団の上で産むしあわせ・快適さに気づき、それが矢島さん自身のお産の原風景になったという。
矢島流お産介助の3原則は、①絶対にひとりにしない、 ②からだに触れる、 ③産婦さんの全てを受け入れる―こと。
「身体が開き、今まで味わったことのない別世界に連れていくのがお産。だからこそおかあさんたちには、『動物になってね、バカになってね』と言っています。本能のままにさせてあげることがひとつの技術なんですね。痛くて強烈な体験であるお産を経験させてあげる、“いのちの原風景を築かせてあげる”こと。それが後に喜びになり、女性が“自分の《産む性》に自信を持って生きていける”ことになるんです」
矢島さんのお話を受けて、早川さんは、「私も助産師さんに子どもを取り上げてもらいました。今日のお話は共感することばかり」とテンポの良いやりとりに。
 早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?
早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?
矢島 満月と新月のときに多いと感じますが、そうじゃないときに生まれることもあります。(現代の女性たちの)身体が変わってきているというのもあるでしょうけれど。だけど、(満月や新月のときのような)潮の満ち引きといったものに導かれて命というものはつながってるなぁと感じます。
産むチカラは一人ひとりのなかに
日本人の生活スタイルが変り、冷え症の女性も多くなった。ちょっと頭が痛ければすぐに薬を飲んで解決できる。椅子の生活、和式トイレから洋式トイレに。何気ないと思える生活スタイルの変化は実は大きなからだの変化が伴う。矢島さんも早川さんもそれぞれに、しゃがめなくなった《女性》や《若者》が多いと実感しているという。
早川 最近の病院では夜中のお産は時間外労働扱いで料金が高くなるので、陣痛促進剤などでお産自体をコントロールするって聞きますし。お産は病気じゃないのになあって、みんながより自然なお産がしたいって声をあげていってシステムを整えていくことが大事だなって思います。産むという野生の力が一人ひとりの中にきっとあると思うんです。
矢島 今、みんな医療に任せてしまっている。自分で産んで自分で育てるっていう感覚があまりないというか。子どもたちに生きる力がつくようにしないとね。
早川 高知では助産院が県内に一軒しかなくって、(助産院で産みたい)妊産婦は他府県に産みに行ってるんです。助産師さんを目指す人たちがもっと増えればこの状況は変わるのになと思っています。
矢島 今の世の中では経済効果としての《出産》なんですよ。国から助成金も出るし。だからこそどういうふうに豊かなお産にもっていくかということが問われていると思うんです。
お産の現場に男性助産師?
早川 (矢島さんの)本を読んで知りましたが、1997年頃から男性助産師の導入に反対されたのですね。
矢島 開業してまもなく助産師会に入りました。男性助産師を導入しようという動きを受けて、助産師会から反対運動をしてほしいと言われたんです。“これはいけない!心もからだもひらくお産のサポートをするのは、やはり女性であるべきだ”と署名運動を全国展開しました。初めて国会に行ったり、いろんな議員さんとも知り合いになって導入は見合わせになりました。
それから4年後でしょうか。国会でまた法案を通す動きが出てきてね。こんどは助産師会が男性助産師の導入に賛成したんです。それぞれの立場はあるものの、わたしは産む女性の性を守りたいという立場で運動を再開しました。時期尚早・女性の羞恥心・プライバシーへの配慮・生命と性の尊厳などを訴え、法案は見送りになりましたが、いつまた再燃するかはわかりません。
(男性がお産の現場にいるなかで)自分のからだをさらけ出すということは女性にとって苦痛なんです。そういうことを堂々と言える世の中になればいいなと思っています。
早川 古代からの長い歴史を考えると、たかだか100年くらいの間に病院がたくさんでき、薬を飲んだり手術をしたりという世の中になりましたが、それまでは薬草を煎じて治したり、民間医療とかいろんなものがあったんですよね。お産も女性たちによって支えられてきたと思います。逆に男性の得意なことと女性の得意なことがあるから産む性としての女性の役割は大事にされるべきじゃないかなって思いますね。
矢島 わたしたちはこういうお産をしたい! という声を出していかないと、と思うんです。命があればいい、簡単にお産が済めばいい、じゃないんですよね。
早川 私の場合は1人目はラ・マーズ法だったんです。最初はそこで分娩台に乗せられたんですが、2回目のときに先生に“これは嫌だからちょっと立ってお産してみる”って言ったら“いいよ! いいよ!”って言ってくださって。好きな音楽を流してくださり、くつろいで産めたんです。今でも交流があってつながっています。2人目の時には上の子も立ち会ってくれて。イキんだときに便が出たことを覚えていて、いまでも話題にされます。(笑)
矢島 便が出るようになると、もうすぐ生まれるんです。喜ぶんです、わたしたちは。
早川 そうなんですか!
矢島 そう。だって肛門だって開いてくるんですもの。
早川 お産は快感だっておっしゃられたのがよくわかります。“バカになる”って話も。今は学校で知識をまず先に学んでしまうので、頭で考えずにからだで感じることが大事なのだと思います。
たとえば食べものだったら賞味期限を見てから、これは危ないってなりますけど、うちでは若い子たちにクンクン嗅いでごらんと言っています。自分の感覚を研ぎ澄まして大事にしていくということが今、求められているんじゃないでしょうか。冷え取りをしたり、おなかの中から呼吸をしたりすることも大事ですね。本の執筆で丹田呼吸法を書いているときにラ・マーズ法を思い出したんですけれど、意識して呼吸をするということはとても大事です。
矢じりから縄文時代に思いを馳せる
早川 矢島さんは縄文時代の矢じり拾いでからだの感覚を習得されたのではないかと思いました。矢島さんの底力はそこから来てるんじゃないかしらって。(笑)
矢島 底力かどうかはわからないですけれど、1個拾うとうれしくってもう何時間も探して。どんな人が、とか空想ばかりしていましたよ。
早川 縄文時代の土偶ってほんとに女性のからだですよね。おなかがぽってり大きくって。それを割ったり、首を落としたり、粉々にしたりしてお祀りしたんですが、赤ちゃんが無事生まれることも育つこともままならなかったから、そうやって土偶をこしらえたんじゃないかなと思うんです。
今日は矢島さんのお話を通して、共通することがたくさんあり感動しました。次の本にお産のことも入れたいなと思います。もっとこういう話を聞いて、自分の感覚を信じる、からだを感じるということに多くの人に触れてほしいと思います。矢島さんは身内が助産師になられていて。わたしもがんばって次の世代の方々にもっと伝えなくっちゃ、と思いました。
矢島 私も、もう少し長生きしたいです。
2016年7月30日対談。
―文責・編集部
- 新しい記事
-
- 花咲くころ、種になるころ、 花咲くころ、種になるころ、それぞれに潜む薬草の力 (7月18日)
- ドクダミ 体内の毒を吸い出す (7月10日)
- トウモロコシの毛 煎じ茶で膀胱炎を治す (7月1日)
- スギナ 内臓のさまざまな痛みに 一条ふみさんとの出会い (7月1日)
- ツユ草 梅雨の後半からぐんぐん育ち、腎臓を守ってくれる (7月1日)
- 梨木香歩図書館で『ほどくよ どっこい ほころべ よいしょ』コメントを掲載していただきました! (4月10日)
- カテゴリー